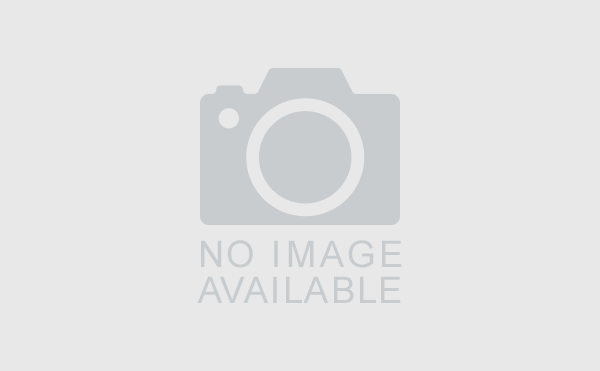日銀の金融システムレポートと不動産価格
下記ブログは、2025年10月25日 当社メールマガジンにて発信したものです。
日銀の金融システムレポートとは
10月23日に日銀の金融システムレポートが公表された。当レポートは、半年に1回公表されるものだが、次の2点を⽬的としている。⼀つは、⾦融システムの安定性を評価すること、もう⼀つは、安定確保に向けた課題について日銀が関係者とのコミュニケーションを深めることである。金融システムの安定性評価の中で、不動産市場や不動産価格に触れていることも多い。今回のレポートでは、不動産にかかる分析内容が豊富であったので、その中から私が興味を持った内容についてご紹介したい。
マンション価格上昇の背景分析
当レポートで、マンション価格上昇の背景分析として、マンション価格上昇の要因分析を行なっているパートがある。マンション価格上昇の要因を「需要要因」と「供給要因」に分けて数値化している。「需要要因」は、新築マンションの発売増加とともに価格上昇が⽣じるようなショックによる影響、「供給要因」は、⼯事費上昇や発売減少とともに価格上昇が⽣じるようなショックによる影響を指す、とされている。
図1の左の2つのグラフをご覧いただきたい。
新築価格も中古価格も、その大半が「供給要因」で説明されるという結果になっている。つまり、工事費の上昇や発売戸数の減少が大きな要因ということである
とすれば、資材価格の高騰や人件費の上昇、人手不足などによる工期の長期化、建築費の上昇という傾向は続いており、「供給要因」の優勢による価格の上昇というトレンドは今後も変わらないのではなかろうか。
(図1)
マンションの需給環境
さらに、図2のマンション空室率も低下しており(データの確からしさはよくわからないが、一応、日銀が採用しているので)、賃貸需要という需給面でのバランスも価格上昇につながりやすい動きになっている。あとは、価格が上昇しすぎて、買い手がいなくなるという売買需要での需給バランスであるが、既に、中心部では富裕層しか買えない価格設定になっているので、大幅な株価下落やリセッションがない限り、そうした層の購買力が落ちることも限定的なのではないかと思う。
実際の価格と推計値の乖離度合い vs. イールドギャップ
次に先ほどの図1の右側のグラフであるが、これは、新築マンション・中古マンションの価格とそれらの推計値との乖離と、賃貸住宅物件のイールドギャップを表したものである。実際の価格と推計値との乖離が、ちょうど、イールドギャップの低下と相関しているようなグラフになっている。解釈の仕方は難しいが、日銀は、「⾜もと、マンション投資にかかるイールドギャップは低下しており、価格上昇期待に基づく投資需要等も反映している可能性がある」としている。
まとめ
これらを総合すると、私見であるが、やはり当面、マンションの価格が下がる大きな要因は見当たらず、価格上昇はそれなりに継続していくしかないであろう、ということになる。
足元、日本株は、高市トレードで出来過ぎの感があるものの、国内・海外とも、トランプ関税の初期段階のような不透明感は消え去っており、経済は巡航速度的に推移していくことが予想される。
マンション価格上昇継続の予想が外れるときは、よほど大きな外的ショックがある時に限られるのではないかと思う。少し楽観的すぎる予想であろうか?
「音楽が鳴っている間は踊り続けなければならない。我々はまだ踊っている。」というのは、2007年当時シティグループのCEOであったチャック・プリンスが語ったとされる有名な言葉だが、さて、我々は、今どのあたりにいるのであろうか?
フォーラムのご案内
先日創設しました不動産に関する情報交換、意見交換を行う当社HP上の「フォーラム」の再案内です。自らは情報提供、意見提供をせず、他の会員の方のやりとりを見るだけのご参加もウエルカムです。
会員登録は、下記「フォーラム会員(無料)登録画面」のボタンを押して、必要事項を登録願います。会員といっても、無料で、何ら義務は発生しません。
会員になってからのログインは、下記「フォーラムログイン画面」からログインできます(弊社HPのトップページにも、下記二つのボタンを用意しています)。
それでは、皆さんのフォーラムへのご参加をお待ちしております。